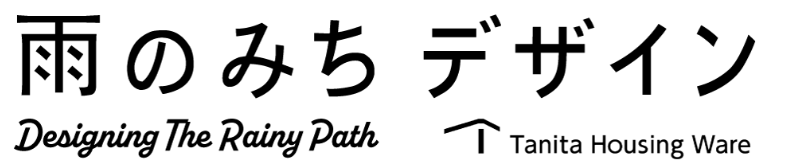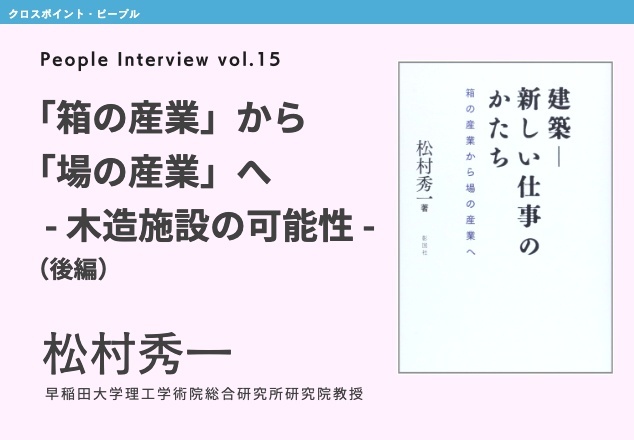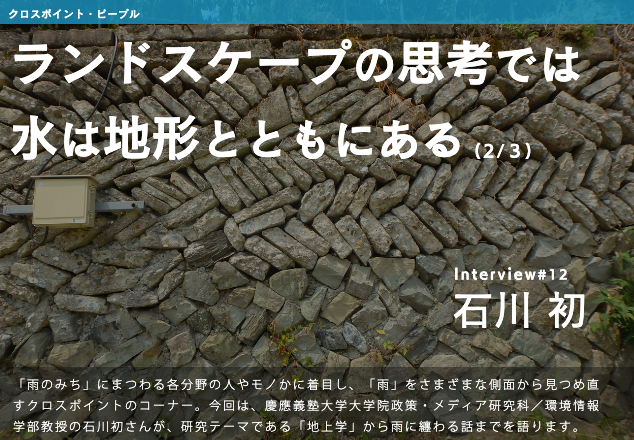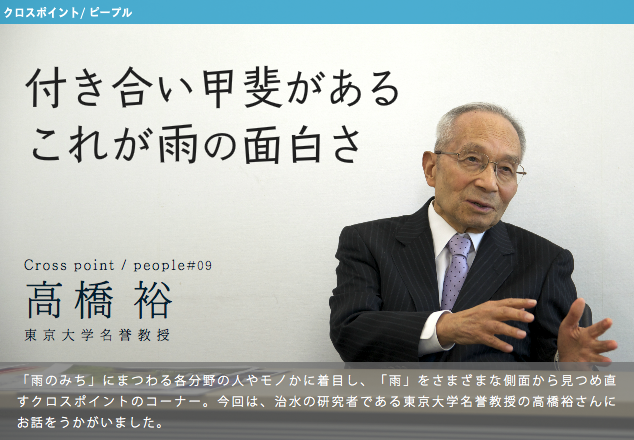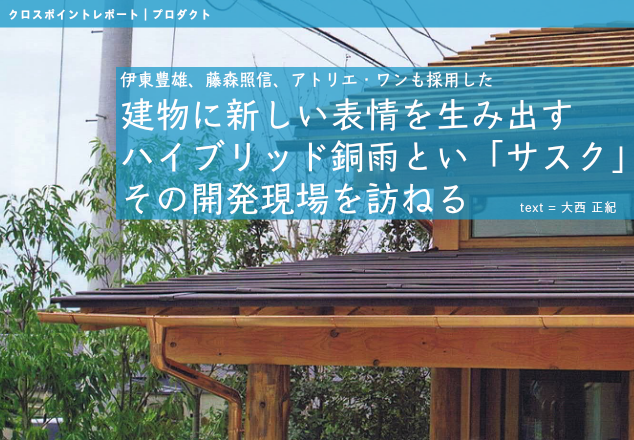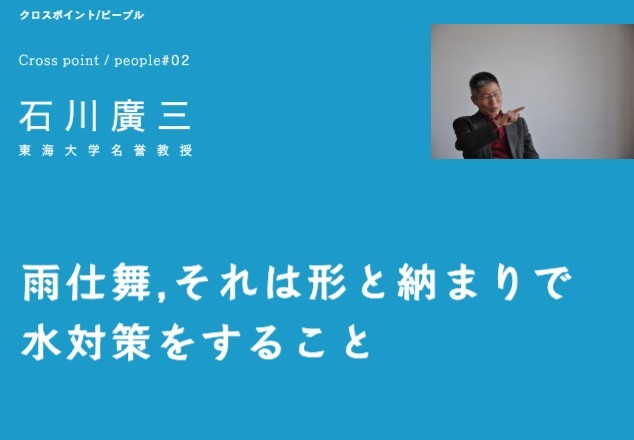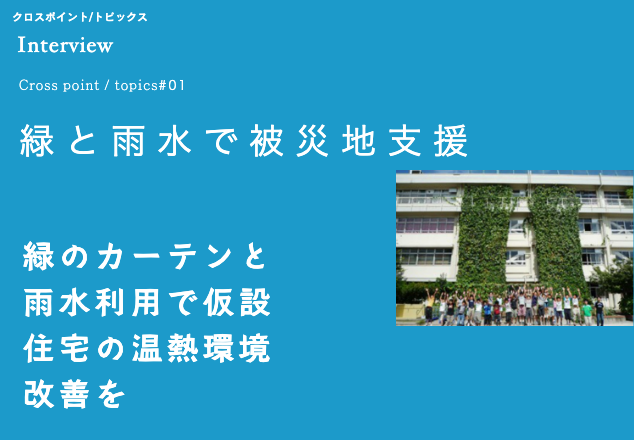取材日:2022年10月28日 インタビュアー:真壁智治、編集:大西正紀
「箱の産業」から「場の産業」へ
- 木造施設の可能性 -(後編)
— 今日伺いたい3番目のポイントは、木造はどう「場の産業」にコミットしていったらいいのかということです。
松村: さきほどお話したプレハブ住宅の場合は、それぞれに作り方が異なるので、それぞれの会社でないと理解することができません。町の工務店が、プレハブ住宅を観ても、まず法律上それを勝手に触ることができない。
その世界に比べると、木造の世界は違います。日本における木造は、いわば誰もが知っていることで、1990年代に北海道で建てた家を、九州の工務店さんが見に行っても、わからないことはあまりありません。そういう意味では、ストックとしての共通理解のベースができています。それが非常に大きな特徴です。
これが今建てられているビル的な木造施設となると、また話が変わってきて、かなりクローズドな世界になっています。中を開けるとそれぞれのゼネコンが違うやり方で特許を取っていたりします。たとえば防火を考えて、柱にモルタルを入れていたり。そうなってくると将来的には、そのゼネコンが建てたものは、そのゼネコンにしか扱えなくなるものになってしまう。
— とても鋭いご指摘ですね。それは部品のクローズド化どころの話ではありません。
松村:木だから触りやすい、理解しやすいという面はありますが、難しい面がたくさん生じていきそうです。一方で、たとえば鉄骨の体育館などは、ものすごくわかりやすくできています。どこの体育館も同じ作り方だから、一気にみんな直せるんです。ところが今の木造の世界は技術開発の時代なので、みんなオリジナリティを競い合っています。こんな構造どうだろう、CLTを使うおう、いや俺はCLT使わない派だとか、いろいろある(笑)。そこは面白い部分ではあるけども、長い目で見ていくと、これらがストックになっていったときにたとえ木造の建物だったとしても、他の工務店では対応できないことが多くなっていくと想定されます。
— 木造施設っていうときに、そういう問題が内包されているんですね。木造施設の規模にもよるでしょうか。保育園や小規模の学校、あるいは図書館から中高層まで、今のゼネコンは中高層の建築物を木造でトライしようとしています。
松村:「場の産業」からずれて「箱の産業」の話になるのですが、今の木造施設は、住宅よりも大きいです。それは、プロジェクトの費用や規模が大きいということでもあります。すると、同じ木造なので、それまで木造住宅をやっていた町場の工務店が関わっているものだと思っていたのですが、実際に工務店の方に聞いてみると、みんなやらないそうなのです。
理由を聞くと、自分たちでリスクマネジメントできる規模ではないと。じゃあ、大きなゼネコンが中規模まで降りてくるかというと、それもそうではないのです。だから、真壁さんがおっしゃる中規模の木造施設に対する需要は一番大きいし、国も補助金をつけているのですが、誰もやらない空洞地帯みたいになっていると思います。
建築計画学としての「場の産業」
— 「場の産業」のもう一つの問題は、それに対する建築計画学が確立していないことかと思います。今若い人たちが模索しているのも、ここでの計画学ではないでしょうか。
松村:それはおっしゃるとおりです。「場の産業」についていろんなところで語ってきましたが、よくよく考えてみると今まで建築学科ではまったく教えてないことだと気づきました。キッチンがアイランド型になると、子どもが手伝いに来るみたいなことは計画学で触れられますが、そこでどのような生活が展開していくかということまでは、考えられていないわけです。建物というのは、「箱の産業」では、とりあえずできて引き渡すまでがメインですが、「場の産業」のメインである実際に箱の中に入って展開される人生というものが、実はまったく関係付けられていないんです。
想定したプランが考えられているけども、生き方までは付き合っていられない。バブルの頃がまさにそうでした。あるディベロッパーに話を聞きに行ったら、マンションの企画は建築学科を出た人に絶対やらせないといいます。理由は、やたらとディテールにこだわるからと仰っていました。だから、商品企画は全部文系出身の社員がやると(笑)。
— (笑)。
松村:これは象徴的な話です。建築の世界に生きる人はハードにこだわるので、人の生き方について考えている暇もない。みんな徹夜で図面を引いていたりしますから。自分自身が生き方、楽しみ方に意識的に生きていないとなかなかわからないですからね。
— 今の30、40代を中心に取り込みながら、新しい計画学へ移行する必要があるかもしれません。完全にしない非完全な状態を要求されてきたとき、塚本由晴さんが言う「非施設型施設」というのか。たとえば図書館であっても、それだけの機能ではない施設。そういうものを作るときに、従来の古典的な計画学ではどうにも立ち行かないという現実に直面しています。
松村:今から20年ほど前に、評論家の芹沢俊介さんにお話をうかがいました。芹沢さんが仰っていたのが、「脱施設・脱家族」でした。芹沢さんは、高齢社会や親が面倒を見てくれない子どもたちの施設をよく観察することが、家族の先端的な現象を捉える上では、良い方法だと考えていました。そうやって観察していくと、高齢者施設と言っていたものがグループホームへと変化してくように、結局さまざまな施設は、どんどん「家」のようになっていきます。
— ホスピスなんかもそうですね。
松村:それらも住宅にどんどん近づいていきます。一方で、住宅は住宅以外の機能を加えていって、施設みたいになっていきます。その境目が、どんどんなくなっていくのだと思います。
— 今現実に起きてることですね。
松村:まさにそうですね。家族がどうして一緒に暮らしているかということは、問わずもがなでした。芹沢さんが不思議な家族を観察していると、前の旦那さんと今の旦那さんと私で暮らしている方がいたり。これは家族なのか?という表現のしづらいタイプがたくさん出てきているそうです。そうなると、その場所で出会い一緒に暮らしているグループホームと、家族だとも言わず一緒に暮らしてるこの人たちとは、何の違いがあるのか。実はあんまり違いはない。そういう時代になってますね、という話を芹沢さんはされていました。すでに20年前に、です。
— プレファブメーカーが提唱してきた二世帯住宅の総括みたいなものも未だになく、うやむやになっています。絵に描いたような健全な二世帯が存在するのは、ほんの一瞬に過ぎません。家族の変容、暮らし方の変容、それらが住宅の変容を求め出していて、それを適えるためにも「完全にしない家」が計画的に求められる時代になってきたのですね。それに「施設」と「住宅」との境目もどんどん曖昧になってくる眺めに「木造」は置かれていることがわかりました。
「愛される建築の行方」
— 松村さんには「愛される建築の行方」についても伺いたいと思っていました。松村さんはご自身の著書『建築の明日へ』で、すべての人が自分の暮らしのために再編集する時代に入ってきた、と書かれていました。そのなかに愛される建築を自分たちなりに練り上げていくような「場の産業」の醍醐味が潜んでいると思いました。それは「場の産業」のビジョンのひとつですよね。
松村:西欧に行くと、市民が建築案内をしてくれるツアーがいろんな町にあります。普通の人が建築を愛しているから、その建物が好きな市民の方がツアーもやっている。でも、日本にはこういうものはありません。日本にはどうしてないのかなと思うのですが、確かに特に愛する理由がなかったりします。
たとえばコルビュジェのサヴォア邸なんて、殆ど短い間しか人が住んでいません。それでも建築の世界ではサヴォア邸は、もうめちゃくちゃ評価が高くて、世界遺産になってしまう。この感覚で人々に建築を愛してくださいと言っても無理なんですよね。
その一方で、昨今の建築の民主化、ストックがあって場をつくるという誰にでもできることが、愛するきっかけになるのではないかと。新築から作ることはできなくても、そこを借りて何か面白い空間に変えるということは、誰もができる。そうなると、自分たちが自分たちの好きなように手を加えたものに愛着が湧くとか、手を掛けた分かわいいと思えるとか、だから、ご近所さんや仲間とセルフリノベーションをするようなことも増えてきているんですよね。工事だけではなくて、場として楽しむものが増えていくと、結果として器である建築も含めて好きになっていきます。
— 愛おしくなっていきますね。
松村:まさにその関係です。コルビュジエのサヴォア邸が好きということは悪いことではありません。それはそれでひとつの世界をつくっていて面白い。どちらかと言うと建築の世界はずっとそれをやってきました。でもそれが、より開かれたものになっていくと問われることが違ってくるわけです。
— 「建築の民主化」や「建築を開く」というなかで「場の産業」がだんだん成熟してくる。そのことによる生活者、住まい手の意識の変容が相当出てきました。特に変わり出したのは使い手が場や建築に対して対話をするようになってきたことです。その流れの上に施設に対して使い手が抱き評価する感情・感覚として、つまり施設対象をカワイイかカワイクナイかの直感的指標から全体を把握する態度なのです。こうした施設との対話が施設を愛する契機となるものなので、リノベーションでは「カワイイ」は絶対的条件ではないでしょうか。
松村:自分たちで触りはじめると、主体的になっていくので、いろんなものを作り手として見るようになっていきます。自分でリノベーションしはじめた人は、人の家に行ったら、この壁はどの壁紙だろう?と、気になってきます。そういう目線で、いろんなものを見られる人が増えていくと、材料やプロダクトについても、建築教育を受けた人とは違うものが流行っていきます。そういうことはこれからもっと変わっていくでしょう。
— これも定常型社会になってきたなかでの新たな動きということができそうです。
松村:そうですね。人口が減り、たくさんの高齢者がいなくなって、次の世代に日本が変わっていくと、まったく違うことになっていきそうです。僕らもいなくなった次の世代の日本がどんなふうになるかは、もう想像もつきません。
設計課題に“雨のみち”
— 最後に、「雨のみち」についてうかがえればと思います。内田祥哉先生の身近にいらして、「雨」の議論は多かったのではないでしょうか。
松村: 昔、内田祥哉先生の講座では、雨漏りについても取り上げていました。重要な問題でしたから。雨はどうやって漏るのか? どうやって屋根の防水はできるのか? 一つひとつが大きなテーマでした。今でこそ非常に専門的になって、タニタさんのようないろんなメーカーも育って、材料もものすごく多様なものが出るようになってきました。けど、雨漏りの研究をしている人は、ほぼいなくなりました。そう、今思い出しましたが、僕らが大学院のときの内田先生の最初の課題が、「樋の見えない軒先の納まり」でした!
— おお!(笑)
松村:当時僕らは、「この課題はなんだろう。何の意味があるんだろう」と思っていました。これが一個目の課題ですからね。ものすごく鮮烈に覚えています。内田先生たちの世代の建築家のなかには、シャープな感じでつくってきて、いきなり樋が出てくることはどうにか避けたいということを強く思われていたと思います。だから、軒先の奥まった屋根内に樋がおさまっていることが、正解とされました。
今では、あまり言われなくなりましたが、僕らが学生のころは設計課題で屋根に谷をつくると、どんな先生でも「屋根に谷を作っちゃ駄目だよ」と指摘してきました。今は、技術も高まり、たとえばタニタさんが解決してくださるので(笑)いろんな形が実現できるから、そういうレベルでの指摘はなくなってきていると思います。それだけ昔は、「谷は作らない」「軒先はこう作る」と設計する側が、前もってよく考えていたのですね。
— 内田先生は開放樋も作られていますね。
松村:屋根ではなくて、カーテンウォールの開放樋ですね。
昔、林昌二さんと池田武邦さんが、内田先生の委員会のために、よくここ(東京大学)に来られていました。そこのバルコニーに林さんが出ていらして、そこから見える文京区役所を感慨深げに眺めていて、そこに池田武邦さんがやって来たんです。僕はお二人に、「カーテンウォールの内装の下地を取ったら、目地のところからホースから出る水のようにピューっと水が出たっていう話を聞ききました」って言ったんですよね。そしたら「そんなことはどこでも起こってるよ」と(笑)。僕はそんなことは知りませんでした。でも彼らが言うには、雨漏りしないカーテンウォールなどないでしょう、と。
建築の世界では、このことはずっと問題でした。ダブルでシールして、片方が切れたらどうなるのか、圧力差がかかるとどうなるかということを、内田先生の世代の方々はさんざん議論してきたのです。それで、内田先生は気圧差をなくして空洞にして、そこに刷毛を入れようと。刷毛を入れたら、雨は下に流れていきます。等圧空間を作るということからも、おそらくタニタさんがつくられてきたような板金仕事の製品もいろいろと調べられていたと思います。
耐震は構造屋さんという専門が確立しているから、構造設計者にお願いします。でも、雨漏りは重要なことにも関わらず専門が確立していないので、設計者自身が中心に考えなくてはいけません。壁の目地、屋根、樋といったことや、溜まった木の葉をどう掃除するかということまでも含めて、設計者がすべてを考えなくてはいけない。そういう必然性によって関心が向いて、内田先生たちはそういう議論をよくされていたのでしょう。でも、今ではそういう話題を建築学科の教育の場で聞くことは、非常に少なくなってきました。
— 自分自身で設計の仕事を始め、はじめてその問題に突き当たり、タニタに相談するケースが非常に増えてきているようです。そういう意味からもタニタは、コンサルティング型のメーカーになることが期待されてきているというふうにも思います。
松村:できた箱を直すとき、たとえばマンションの大規模修繕などでは、まさにそういうことが求められています。特に屋根防水を変えるときが最も大規模な修繕となります。これまでは屋根防水は非常に大きな課題でしたが、今の技術のように防水が何十年も保つようになってくると、それもだんだんと変わるかもしれません。いずれにしても、雨とは建築にとって非常に中心的な課題であり続けることは、今後も変わらなそうです。
— 木造施設を巡る近況が松村さんから指摘されました。それは「場の産業」への移行が「木造施設」を考えてゆく上での重要な局面を含み、計画上も、構法上も、新たな対応が強く求められていることが良く分かりました。
また同時に、住まい手側からのセルフリノベーションなど、住まい手側からのイマジネーションも、これからの木造施設市場には欠かせないものになってくるのを感じました。これらは間違いなく「木造施設」に於いては作り手と使い手との距離がより近くなることを意味していると思います。
本日は、大変ありがとうございました。
松村秀一
(まつむら・しゅういち):1957年生兵庫県生まれ。1980年東京大学工学部建築学科卒業。1985年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了。東京大学工学部建築学科専任講師、助教授を経て、2006年から2023年3月まで東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授、特任教授を歴任。2023年4月から早稲田大学理工学術院総合研究所の研究員教授。主な著書に『空き家を活かす』(朝日新聞出版)、『ひらかれる建築』(ちくま新書、2016)、『「住宅」という考え方』(東京大学出版会、1999)など。2005年日本建築学会賞(論文)、2015年日本建築学会著作賞などを受賞。