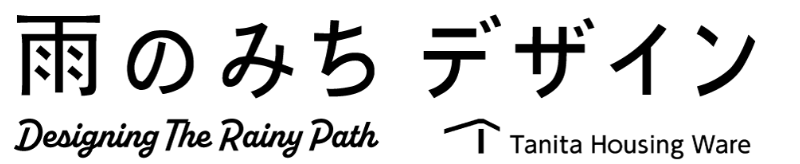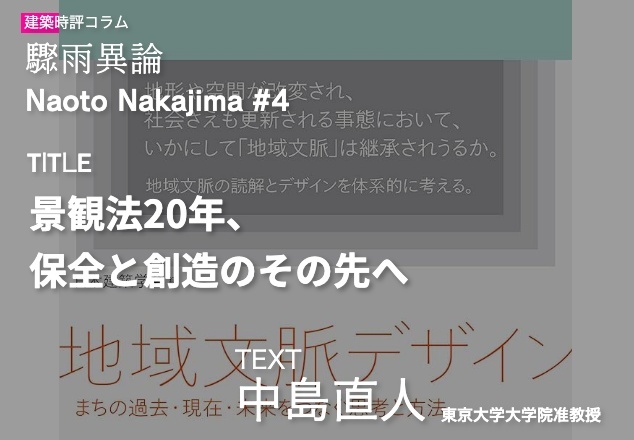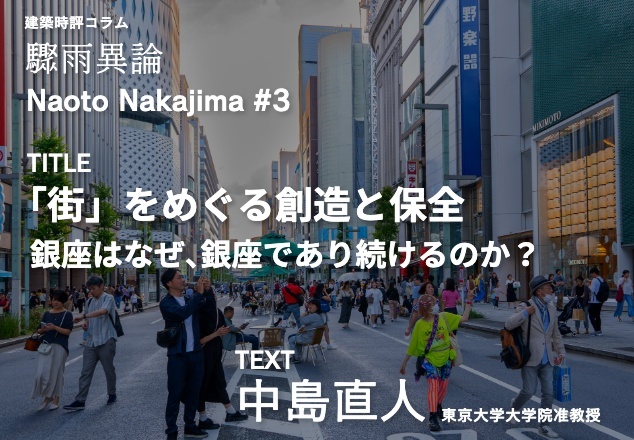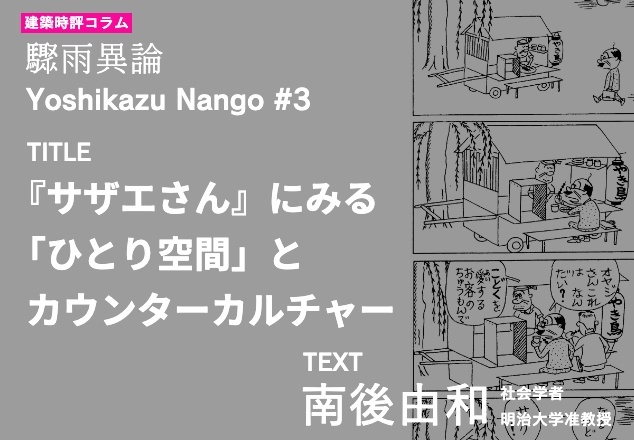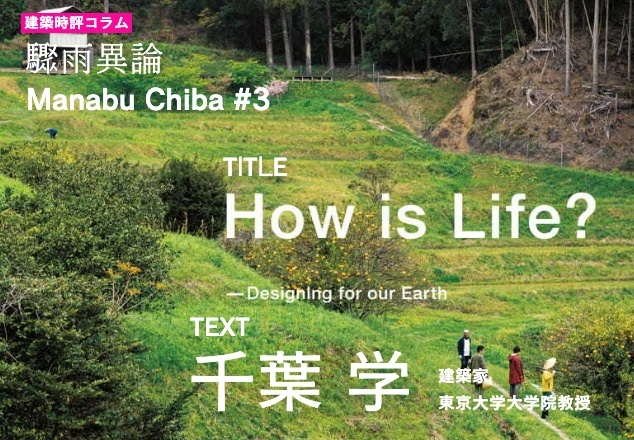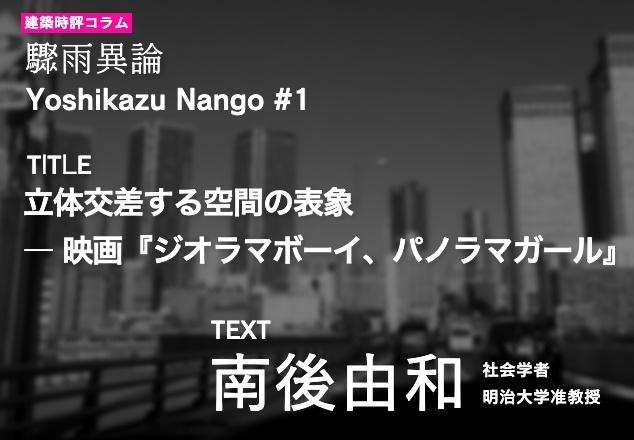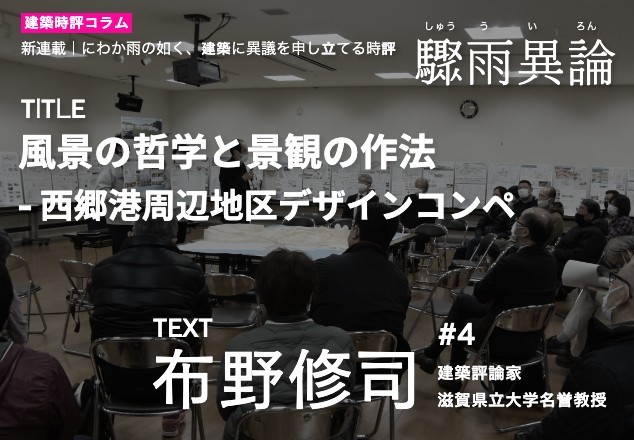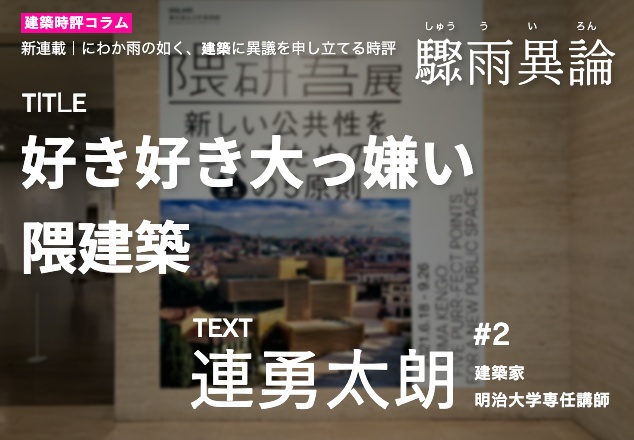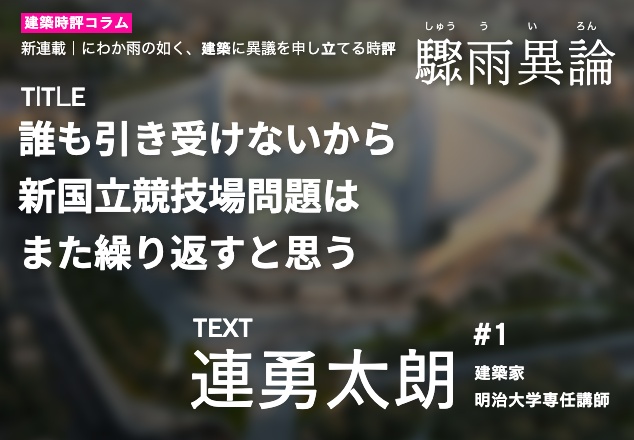連載|にわか雨の如く、建築に異議を申し立てる時評

その不意さ加減の面白さ、深刻さを建築の時評に。建築のここが変だ、ここがオカシイ、建築に声を上げる「驟雨異論」。 にわか雨が上がるのか、豪雨になるのか!?

1979年大阪府生まれ。明治大学情報コミュニケーション学部准教授。社会学、都市・建築論。東京大学大学院学際情報学府博士課程単位取得退学。デルフト工科大学、コロンビア大学、UCL客員研究員などを歴任。主な著書に『ひとり空間の都市論』(ちくま新書、2018)、『商業空間は何の夢を見たか』(共著、平凡社、2016)、『建築の際』(編、平凡社、2015)、『文化人とは何か?』(共編、東京書籍、2010)など。
URL:個人ウェブサイト
明治大学情報コミュニケーション学部南後ゼミ
YOSHIKAZU NANGO #4 2023.4.6
距離感・脱皮する都市・スケール

天王洲エリアから東京湾岸エリアの輪郭を見る(photo = Alex Knight)
連載第1回では映画、第2回ではVR・メタバース、第3回では漫画などのメディアにおいて表象される空間について書いてきた。各回では互いに異なるトピックを扱ってきたように見えるかもしれないが、「メディアのなかの空間」をめぐる記述という点は一貫していた。いわば連載のタテ糸が「メディアのなかの空間」であったわけだが、最終回は、第1回とその他の回のヨコ糸/伏線について書くことにしたい。
まず第1回の「立体交差する空間の表象――映画『ジオラマボーイ・パノラマガール』」と、第2回の「バーチャル素材化する渋谷」のあいだにあるヨコ糸/伏線とは何か。それは二つの地理的に離れた場所の「距離感」と「脱皮する都市」の姿である。
映画『ジオラマボーイ・パノラマガール』では、主人公たちが暮らす東京湾岸エリアのみならず、その場所でしか経験できない何かが期待される渋谷という、二つの地理的に離れた場所の「距離感」が描かれている。第1回では「立体交差する空間の表象」について取り上げたが、『ジオラマボーイ・パノラマガール』においては、都心から外縁の東京湾岸エリアへ向けられるまなざしと、外縁から都心へ向けられるまなざしも交差しているのだ。
神奈川ケンイチがスケートボードに乗り、ナンパに出向く場所は渋谷のMIYASHITA PARK付近である。渋谷ハルコがゆりかもめに乗って出かけ、夜のクラブに繰り出す場所も渋谷である。1980年代後半のバブル期に出版された岡崎京子の漫画が原作ということもあり、いまだ渋谷がそこにしかない何かを期待する場所として描かれている点はご愛嬌だが。
ある場所を対象化するには、その場所からいかに距離をとるかが重要になってくる。その点、この映画では、エンディングに象徴されるような東京湾岸エリアから都心を遠望するカメラワークに加え、移動手段のさまざまな速度を織り交ぜながら東京湾岸エリアと渋谷との「距離感」を描くことで、その双方を対象化している。ここでいう「距離感」とは、物理的距離と心理的距離が重なり合ったものとしてある。
この映画が撮影された2019年の東京湾岸エリアと渋谷に共通するものとして、スクラップ・アンド・ビルドされる工事中の風景がある。そのなかでも印象的なのは、「脱皮する都市」の皮とでもいうべき――真壁智治『臨場 渋谷再開発現場』でも取り上げられている――建設現場の仮囲いの防塵ネット・養生シートである[※1]。
たとえば東京湾岸エリアでは、防護ネットで覆われた工事中のオリンピック選手村(晴海フラッグ)が登場する。オリンピック選手村は、主人公の妹たちが隠れん坊をする秘密基地となっている。ビニルの養生シートが風でゆらめく様子が印象的だ。渋谷では、同じく工事中の防護ネットで覆われたMIYASHITA PARKや外構工事中の渋谷PARCOが映っている。工事中に一時的に垣間見られるこれらの皮は、スクラップ・アンド・ビルドされ、変貌していく都市が一時的に見せる「脱皮」の姿だといえるだろう。
次に、連載第1回で扱った東京湾岸エリアと、第3回で扱った「ひとり空間」のあいだのヨコ糸/伏線とは何か。それは「スケール」である。XSサイズの「ひとり空間」とXLサイズの東京湾岸エリアは、空間サイズという点において対照的な関係にある。前者は狭小のヒューマン・スケールであり、細部まで把握しやすいが、後者は非ヒューマン・スケールであり、茫洋としており捉えがたい。
大半の人びとが足を運ぶ東京湾岸エリアは、ゆりかもめの駅周辺などに限定されているだろう。実際には、その背後にある港湾施設や物流倉庫、エネルギープラント、コンテナ、ガントリークレーンなどが集積するエリアの方がはるかに広大な面積を占めるが、それらのエリアは人びとの認知地図において仔細に描かれることはない。
東京湾岸エリアの捉えがたさは、その輪郭の不定形さにも起因している。埋立地の造成をはじめとして、東京湾岸エリアの輪郭は時代の推移とともに書き替えられてきたからだ。1973年から中央防波堤内側埋立地、1977年から外側埋立地、1998年からは新海面処分場の埋立てが始まった。中央防波堤内側埋立地は、その後、「海の森」となり、東京オリンピック・パラリンピック2020ではボートやカヌーの競技会場として使用された。
これらの埋立地には、河川の浚渫や下水処理で生じる泥に加え、都心部で排出されるゴミや建設現場の残土が運び込まれた。用地不足のため、新たな埋立地が造成され、東京湾岸エリアの輪郭はその度に書き替えられてきた。人口増加や建築物の高層化と連動して、埋立地が次々と造成されていったことを鑑みるならば、東京という都市の「垂直方向」への拡大と、「水平方向」の拡張は連動していたと見なすことができるだろう。
東京湾岸エリアの輪郭は単に地理的、空間的なものとしてあるだけではなく、社会的なものとしてある。エッジでもある東京湾岸エリアには、時代ごとに「社会の夢」が投影されてきた。たとえば1980年代から90年代は、情報化や国際化と連動した「フロンティア」や「ウォーターフロント」として、近年では、東京オリンピック・パラリンピック2020の開催やそれにともなう再開発の場として。
ところで、従来の都市論の多くは、新宿・渋谷などの盛り場を対象とするものであれ、郊外のニュータウンを対象とするものであれ、主に人びとが労働や消費をし、居住する生活圏について論じてきた。
それに対し、人びとの生活を支えるインフラが集積し、居住する生活圏の「後背地」である東京湾岸エリアは議論の俎上に載せられる機会が少なかった。東京湾岸エリアについても、たとえば『シン・ゴジラ』などの映画、特撮ヒーローものや刑事ドラマなどの舞台となってきた。
映画やテレビにおける東京湾岸エリアの表象も興味深いが、茫洋として捉えがたい東京湾岸エリアにアプローチし、その巨大さを認識するうえでは、「地図」というメディアが相性がよい。埋立地や埠頭などの輪郭を認識可能なものにするうえで重要な役割を果たしているメディアは、地図にほかならない。
東京湾岸エリアの輪郭にかぎらず、地図に引かれた境界線は固定的なものでもなければ、永続的なものでもない。現在のウクライナとロシアをめぐる領土問題が示しているように、地図に引かれた境界線は政治的、歴史的に複雑な意味合いを持っている。
このような地図のなかに引かれた境界線に加え、近年は地図とその他のメディアとのあいだの境界も興味深い対象となりはじめている。従来は二次元の紙地図が主流であったが、更新可能性、リアルタイム性、共有可能性、パーソナライズ化、データの重ね合わせなどの特徴を持つ、デジタル地図が普及して久しい。Googleマップでもすでに3D表示は実装されていたが、連載第2回で扱ったVR・メタバースの台頭によって、地図とその他のメディアの境界がますます曖昧になってきている。
VR・メタバース上の「バーチャルシティ」は、ひとつには、国土地理院の基盤地図情報などをもとに作成されていることからもわかるように、「地図的性格」を持ち合わせている。もうひとつには、建物の寸法や高さを正確に反映させ、陰影やテクスチュアの解像度などを設定できるという点では、建築の「模型的性格」も持ち合わせているようにも見える――VR・メタバース上の「バーチャルシティ」に物質性は希薄であるが。
では、VR・メタバース上の「バーチャルシティ」の空間体験をいかに記述できるだろうか。この問いについて考えるためのヒントのひとつは、地図と模型に共通する性質である「スケール」にあると考えている。
[※1] 中野豪雄・南後由和監修、武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科学生有志・明治大学情報コミュニケーション学部南後ゼミ著『Tokyo Scope 2022』(Tokyo Scope Books)では、「脱皮する都市」というテーマの特集を組んだ。目次などの詳細は、https://note.com/nango_seminar/n/n32ef25b17698を参照。
|ごあいさつ
2023年度4期の建築・都市時評「驟雨異論」を予定通り配信することができました。 4期を担ってくださった小野田泰明、中島直人、寺田真理子の三氏に厚く御礼申し上げます。ご苦労様でした。 建築・都市を巡る状況は、平穏なものではありません。 民間資本による都市再開発の乱立と暴走、建築建設資材の高騰化と慢性的な人手不足、無策なまま進行する社会の高齢化と縮小化と格差化、気候変動と「with・コロナ」そしてオーバーツーリズムの波etc、克服が容易でない大きな課題が山積状態にあり、今こそもっと建築・都市へ「ここがオカシイ」と声を上げなければなりません。批評の重要さが増している。 その上からも「驟雨異論」の役割は、貴重になります。ここから声を上げてゆきましょう。 2024年度5期では 貝島桃代、難波和彦、山道拓人、各氏のレビューが登場します。 乞うご期待ください。
2024/04/18
真壁智治(雨のみちデザイン 企画・監修)
|Archives